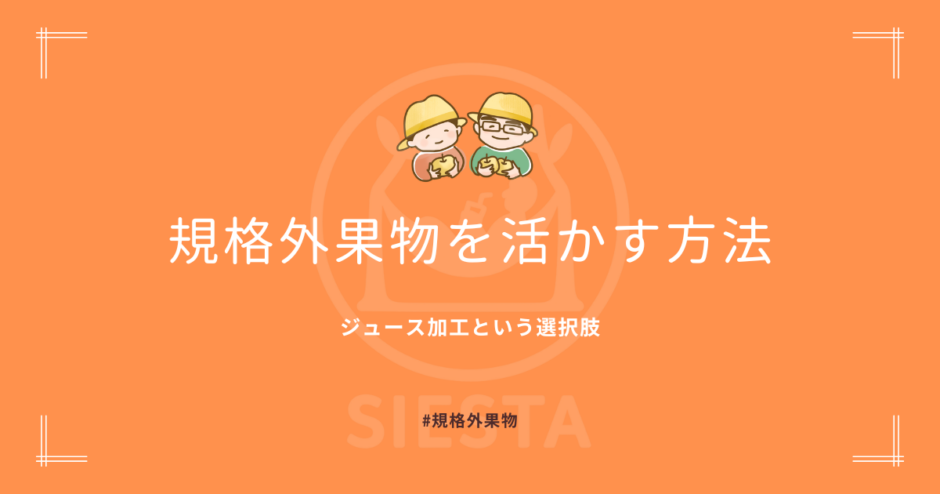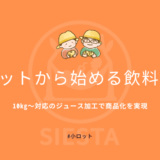「味は問題ないのに、出荷できずに捨ててしまう…」農家や商品開発担当者、自治体の方のなかには、そんな「規格外果物」の扱いに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
形が少し悪い、サイズが小さい、表面に小さな傷がある。そんな理由だけで、丹精込めて育てた果実が廃棄されてしまうのは、生産者にとって経済的にも精神的にも大きな負担です。「どうにか活かせないか」と思いながらも、加工先が見つからない、小ロットでは断られる、販路がない…といった壁にぶつかり、結局そのまま廃棄せざるを得ないケースが後を絶ちません。
この記事では、そんな規格外果物を「価値ある商品」へと変えるジュース加工という選択肢をご紹介します。小ロット対応、無添加製造、そして商品化後の販路支援まで。廃棄せざるを得なかった果実に、新しい価値と収益を生み出す方法を、実務者目線で詳しく解説します。
かんたん30秒でお問い合わせ可能!
規格外果物とは?なぜ廃棄されるのか

市場に流通する果物には「等級」や「サイズ」といった厳しい基準があります。例えば、りんごであれば直径何センチ以上、梨であれば重量何グラム以上、いちごであれば形が整っていること。これらの基準は、流通の効率化や消費者への均一な商品提供を目的に設けられたものです。
しかし、農作物は自然の産物。天候や土壌、生育環境によって、どうしても形や大きさにばらつきが生まれます。わずかに形が歪んでいたり、サイズが小さかったり、表面に小傷があったりするだけで、「規格外」として出荷できない果物が多く存在します。
実際、規格外として廃棄される農産物は年間約200万トンにも達し、これは全収穫量の約6%に相当するという推計もあります。これは果物だけでなく野菜も含む数字ですが、果樹農家にとっても決して他人事ではない現実です。
農家の視点から見ると、この規格外果実は「労力と時間をかけて育てたのに、収入にならない果実」です。肥料代、水やり、剪定、病害虫対策。すべて同じようにコストと手間をかけているにもかかわらず、見た目だけで価値がゼロになってしまうのです。
規格外の果物でも、味や栄養価は正規品とまったく変わりません。むしろ、完熟して自然落下した果実などは、糖度が高く風味豊かなものも少なくありません。
それでも、見た目重視の市場構造のなかでは「商品」として扱われず、廃棄対象となってしまいます。スーパーの店頭に並ぶ果物は、形が揃い、傷一つないものばかり。消費者もそれが「当たり前」だと感じているため、形が悪いものは手に取られにくいという現実があります。
この「味は同じなのに売れない」という矛盾が、規格外果物問題の根本にあります。生産者は「もったいない」と感じながらも、現実的な販路がないため、やむなく廃棄するしかない。これが多くの農家が直面している状況です。
農林水産省によると、平成30年度の国内の食品ロス量は約600万トンで、その一部は規格外の農産物に起因しています。食品ロスには「事業系」と「家庭系」がありますが、規格外農産物は主に事業系食品ロスに含まれます。
国際的にも、SDGs(持続可能な開発目標)のターゲットの一つとして、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させることが掲げられています。
規格外果物の活用は、単なる「もったいない精神」だけでなく、地球規模の環境課題に向き合う取り組みでもあるのです。廃棄される果物を減らすことは、焼却処分による二酸化炭素の排出削減、埋立地の負担軽減、そして限られた資源の有効活用につながります。
「活用しよう」と思っても、ぶつかる3つの壁
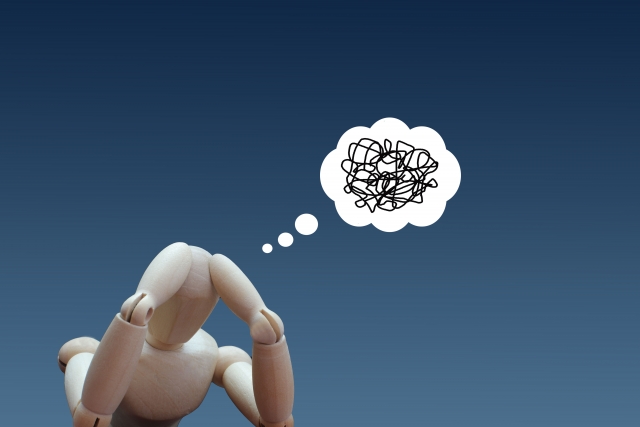
「規格外果物をどうにか活かしたい」。そう考える農家や自治体、商品開発担当者は少なくありません。しかし実際に動き出そうとすると、次のような「壁」にぶつかります。
「ジュースにして売れればいいのに」と思っても、自分たちで搾汁機や加熱殺菌装置を揃えるのは非現実的です。特にHACCP対応となると、設備投資だけでなく、衛生管理体制の構築、記録の保管、定期的な検査など、専門知識と継続的な運用が求められます。小規模な農家や自治体では、これらを一から整えるのは非常にハードルが高いのが実情です。
さらに、委託加工先を探しても、地域にそういった工場がなかったり、問い合わせても「最低ロット500kg以上」と言われて断られたり、簡単には見つかりません。栃木県内にも果実のジュース加工を請け負う業者は限られており、選択肢が少ないのが現状です。
また、一般的な食品加工工場は大量生産を前提としているため、小規模な依頼には対応していないケースがほとんど。「まずは試しに少量だけ作ってみたい」という段階で、すでに選択肢が限られてしまうのです。
多くのジュースOEM業者は、最低でも500kg以上の果物が必要です。しかし、例えば自然落下で収穫された規格外果実が100kg程度しかない場合、その時点で依頼を断られてしまうケースがあります。
「とりあえず少しだけジュースにしてみたい」「試作品を作って、道の駅やイベントで反応を見てみたい」「ふるさと納税の返礼品として小ロットでテスト販売したい」。こうした小規模なニーズは、実際には非常に多いのです。
しかし、大手の加工業者にとっては、小ロットの案件は採算が合わないため受けられません。結果として、小規模農家や自治体の「ちょっと試してみたい」という気持ちが、最初の段階で挫折してしまうことが少なくありません。
また、果樹の種類や収穫時期によっては、一度に大量の規格外果実が出るわけではなく、少しずつ発生するケースもあります。そうした場合、「500kgになるまで待つ」という選択肢は現実的ではなく、結局廃棄せざるを得ないのです。
仮にジュース加工ができたとしても、それを売る仕組みがなければ収益化にはつながりません。
道の駅やEC、ふるさと納税などでの販売には、ラベルデザイン、成分表示、栄養成分分析、価格設定、商品写真の撮影、販促コピーの作成、配送方法の検討など、多くの準備が必要です。さらに、食品表示法に則った正確な表示や、アレルギー表示、賞味期限の設定なども必要になります。
農家の方や自治体の職員がそれを1から用意するのはハードルが高く、「作ったまま在庫になってしまう」「倉庫に眠ったまま賞味期限が切れてしまう」というケースも実際にあります。
また、どんなに良い商品を作っても、「誰にどうやって届けるか」という販路戦略がなければ、売上にはつながりません。「ジュースを作る」ことと「ジュースを売る」ことは、まったく別のスキルと知識が必要なのです。
かんたん30秒でお問い合わせ可能!
小ロット・無添加で対応できるジュース加工という選択肢

そんな課題を解決する選択肢として注目されているのが、小ロット対応可能で、無添加・HACCP対応のジュース加工サービスです。
「ちいさなジュース工房シエスタ」では、10kgからの加工に対応しています。一般的な加工業者が500kg以上を最低ロットとしているのに対し、この差は非常に大きなメリットです。
なぜ小ロットに対応できるのか?その理由は、もともと果樹農家だった経験を活かし、農家の悩みを熟知しているからです。「少量でも無駄にしたくない」「まずは試してみたい」という声に応えるため、小回りの利く設備と柔軟な体制を整えています。
例えば、以下のようなケースでも対応可能です。
・自然落下したりんごが50kgだけある イベント用に少量だけジュースを作りたい
・新商品のテスト販売として100本だけ製造したい
・ふるさと納税の返礼品として、まずは小ロットで試したい
「まず試してみたい」「少量の規格外果実を活かしたい」といった声に応えられる柔軟さが特長です。大手にはできない、小規模農家や自治体に寄り添ったサービスといえます。
保存料・香料・着色料などを一切使用せず、果物本来の風味を活かした無添加ジュースを提供しています。消費者の健康志向が高まる中、「余計なものを加えない」という姿勢は、商品の大きな強みになります。
さらに、HACCPに対応した施設で製造するため、自治体との連携事業やふるさと納税での出品、学校給食や公共施設での提供など、厳しい基準が求められる場面でも安心して使えます。
HACCPとは「Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析重要管理点)」の略で、食品の安全性を確保するための国際的な衛生管理手法です。原材料の受け入れから製造、出荷までのすべての工程で、危害要因を分析し、重要な管理点を定めて継続的に監視・記録します。
この体制が整っていることで、「安全性を証明できる商品」として、販路拡大の可能性が大きく広がります。
繁忙期を除けば、受付から加工・納品まで最短で当日対応も可能です。これは、大手の加工業者では実現しにくいスピード感です。
例えば、以下のようなケースで役立ちます。
・週末のイベントに間に合わせたい
・急な注文が入ったので追加生産したい
・収穫したばかりの新鮮な果実をすぐに加工したい
また、容器についても柔軟に対応可能です。瓶詰め、パウチ、ペットボトルなど、用途や予算に応じて選択でき、商品展開の幅が広がります。瓶詰めは高級感があり贈答用に最適、パウチは軽量でイベント販売に便利、ペットボトルは日常使いに向いているなど、それぞれに特徴があります。
商品化後の「売れる仕掛け」まで伴走支援

「加工して終わり」ではなく、商品化後の販売まで見据えた伴走支援が、シエスタの大きな特徴です。
ジュースとして完成しても、ラベルが味気なかったり、デザイン性が乏しいと売れ行きに大きく影響します。特に道の駅やECサイトでは、数多くの商品の中から選ばれる必要があるため、「パッと目を引くデザイン」と「商品の魅力が伝わるコピー」が不可欠です。
シエスタでは、ラベルデザインを提携デザイナーと共にサポートします。成分表示や栄養成分表の作成など、販売に必要な要素を整えることで、売れる商品づくりをお手伝いします。
具体的には、以下のようなサポートが可能です。
・成分表示や栄養成分表の作成代行
・食品表示法に則った正確なラベル表示
・販促コピーの作成アドバイス
「どう見せるか」「どう伝えるか」まで含めてサポートすることで、商品が「売れる仕組み」を一緒に作り上げます。
商品ができても、「どこで売るか」が決まっていなければ収益化にはつながりません。
シエスタでは、地元・栃木県の道の駅や直売所など、既に繋がりのある販路に加え、ECモール・ふるさと納税ポータルなどへの出品サポートも可能です。販路を一から探す手間を減らし、「作った後どう売るか?」という不安を解消します。
具体的な販路の例として、以下が挙げられます。
・道の駅・直売所:地元の観光客や地域住民に直接アピール
・ECサイト(楽天・Amazon・自社サイト):全国の消費者にリーチ
・ふるさと納税ポータル:自治体の返礼品として安定的な需要を確保
・飲食店・カフェ:メニューの一部として採用してもらう
・企業のギフト用途:法人向けの贈答品として提案
また、販路ごとに求められる価格帯、パッケージ、プロモーション方法が異なるため、それぞれの販路に最適な商品づくりと売り方を一緒に考えます。
フードロス削減と収益化を両立する、新しい農業の形へ

廃棄されていた果物を、ただのジュースとしてではなく「ブランド商品」として再生することは、農業におけるアップサイクルとも言えます。
「捨てるしかなかった果実」が、「収益を生む商品」に変わる。この変化は、農家の収入向上だけでなく、地域全体のブランド価値を高めることにもつながります。
例えば、「○○町の規格外りんごジュース」として商品化することで、地域の特産品としての認知が広がり、観光資源としても活用できる可能性があります。また、「環境に配慮した取り組み」として自治体の広報や地域メディアに取り上げられることで、さらなる認知拡大にもつながります。
その第一歩が、適切な加工と販売の仕組みを持つパートナーと出会うことです。一人で悩むのではなく、専門知識を持ったパートナーと一緒に進めることで、成功の可能性は大きく高まります。
生産・加工・販売までを一貫して行う6次産業化の一環として、規格外果実の活用は地域資源の循環に貢献します。
6次産業化とは、1次産業(生産)× 2次産業(加工)× 3次産業(販売)= 6次産業という考え方で、農家が生産だけでなく加工・販売まで手がけることで、付加価値を高め収益を増やす取り組みです。
また、フードロス削減・地産地消・雇用創出という文脈でも、SDGsを意識した取り組みとして評価されています。特に以下のSDGs目標に貢献します。
・目標2(飢餓をゼロに):食料資源の有効活用
・目標12(つくる責任 つかう責任):持続可能な生産と消費
・目標13(気候変動に具体的な対策を):廃棄物削減によるCO2排出削減
企業や自治体がSDGsへの取り組みを求められる中、規格外果実のジュース化は、具体的で分かりやすい成果として対外的にアピールできるという副次的なメリットもあります。
最初から大規模に始める必要はありません。まずは10kgから、気軽にジュース加工を相談してみてください。
「こんな少量でも本当に大丈夫?」「費用はどれくらいかかる?」「どんな容器が選べる?」「販路はどうすればいい?」。どんな小さな疑問でも、まずは相談することが第一歩です。
小さな一歩が、やがて地域ブランドの確立や安定収益の礎となります。実際に動き出してみることで見えてくる可能性もたくさんあります。
「規格外果実、捨てるしかない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。一緒に、新しい価値を生み出しましょう。
かんたん30秒でお問い合わせ可能!
 ジュース工房シエスタ
ジュース工房シエスタ